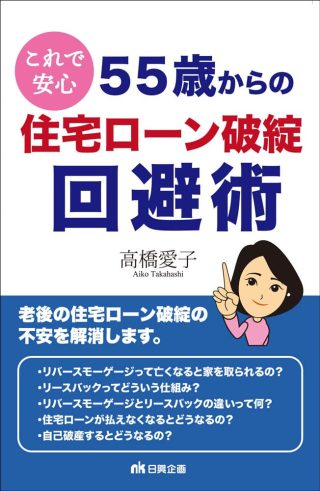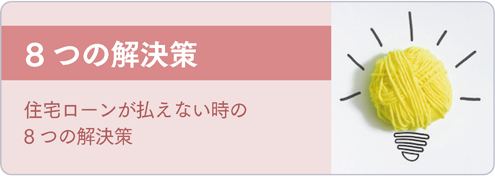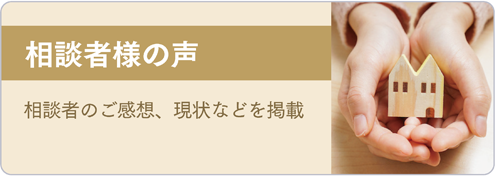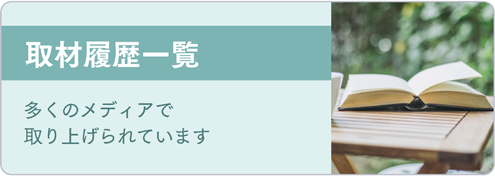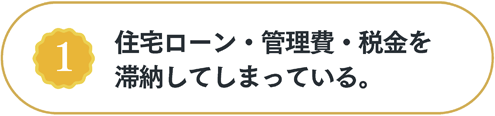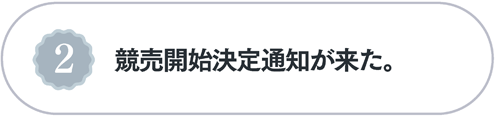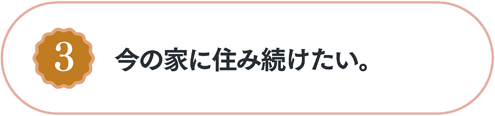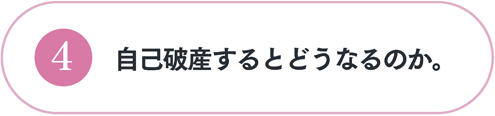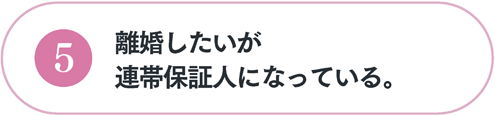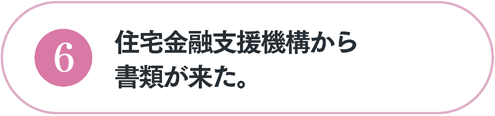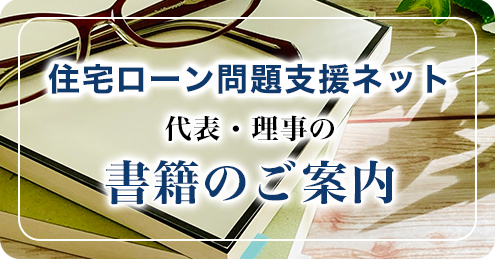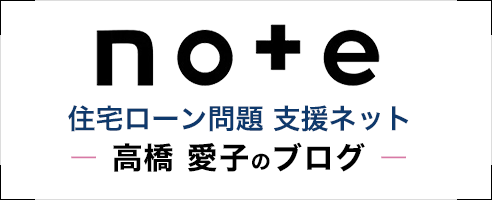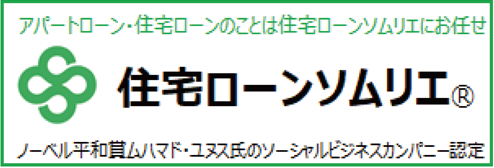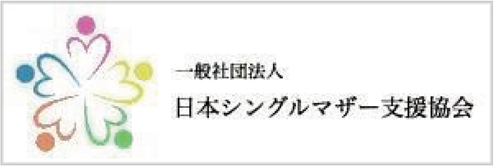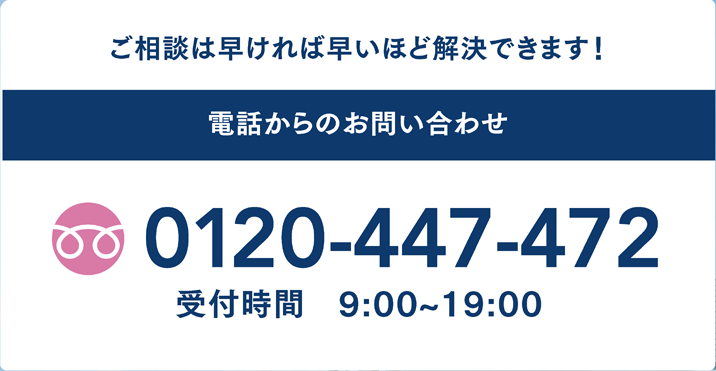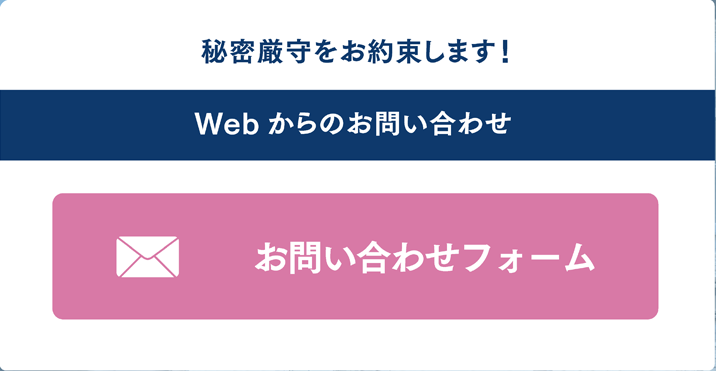住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
皆さんは、自宅の査定を取ったことはありますか?
当NPOは住宅ローン問題を抱える方の支援活動をするという性質上、無料相談の面談中に「査定」という言葉が出るのは日常的なことなのですが、お話をうかがっていると、意外と自宅の査定を取ったことがある方は少ないんだな、という印象があります。
いちばん大事な情報は正確な時価
ご相談の内容は多岐にわたりますが、どんな場合でも、面談で最初にうかがうのはその方の現状を把握するための情報です。正確なローン残高、現在の返済状況、本人の資産状況を聞き、それから詳しい相談内容と、ご本人の希望をうかがってアドバイスさせていただいています。
その際に、いちばん大事な情報が不動産の価格(自宅の時価)です。不動産は市場や景気の影響を受けやすく、価格の変動も大きいですから、「いくらで売りたい」という希望はひとまず横に置いて、まずは正確な時価を把握するために査定を取る必要性をお伝えしています。
町の不動産屋やポータルサイトの利用も
査定を取るのは、難しいことではありませんし、「いますぐ家を売る気がないなら取ってはいけない」というものでも、もちろんありません。
たとえば町の不動産屋さんに頼めば取ることができますし、インターネットで「一括査定 不動産」と検索すれば、数社の不動産会社が登録しているポータルサイトがすぐに出てきますので、こういったものを利用するのも方法です。
「売るかもしれないから、内密に価格を知りたい」「離婚を考えていて、夫に内緒で査定額を知りたい」など、理由がデリケートな場合、町の不動産屋さんに依頼するのは気後れすることもあるでしょう。そんな時はポータルサイトを使ってみてください。ただ、一度査定申込みをすると、そこに登録している不動産会社から営業の電話がかかってくることはあるかもしれません。また、個人情報をそれなりに入力しないと申込めないケースもあるので、いずれも一長一短な面があることは否めません。
しかし繰り返しになりますが、問題の解決策を探るためにはどうしても正確な時価情報が必要なことは、ご理解いただければと思います。
不動産には5つの価格がある
ところで、不動産の価格にはどんなものがあるのでしょうか。
聞き慣れない言葉だと思いますが、不動産は「一物五価(いちぶつごか)」と言って、ひとつの不動産に対して5つの異なる価格があります。
①公示地価:毎年1月1日時点での、1地点(標準地)につき不動産鑑定士2名以上による鑑定評価をもとに、3月に国土交通省の不動産鑑定委員会が公示する土地の価格。(※ネットで確認できます。令和7年公表はこちら)
②基準地価:毎年7月1日時点での、1地点(標準地)につき不動産鑑定士1名以上による鑑定評価をもとに、9月に各都道府県が公表する価格。公示地価の補完的役割という位置づけ。(※個別地点をこちらから検索できます)
③路線価:毎年1月1日時点での価格を国税庁が評価し、7月に公表。前面道路の土地の1㎡あたりの価格で、相続税や贈与税の計算に使われる。(※ネットで確認できます。令和6年公表はこちら)
④固定資産税評価額:市区町村が3年に一度評価し、固定資産税や都市計画税の計算に使われる。(※ネットでは確認できません)
⑤実勢価格:実際に取引されている価格。いわゆる時価。(※ネットでは確認できません)
価格は決まった時点でのもの、一般市況から出すもの、さまざま
①と②は、国が公表している価格としては実勢価格に一番近いと言われています。ただ、いずれも決まった時点での調査価格であり、必ずしも実勢価格と同じではないため、時価の方が高いことも往々にしてあります。
③と④は、国や地方自治体の課税金額を算出するための価格で、路線価は公示地価の8割程度、固定資産税評価額は公示価格の7割程度の水準で設定されています。
⑤の実勢価格は、市場の変化や物件の個別要因(周辺環境、接道、日当り、地形、高低差、建物の間取り・グレード・維持状況等)によって変わるため、実際に不動産市場で取引をしている不動産業者に出してもらうのが一番正確です。ただし、その査定額も絶対に売れる額というわけではなく、売主・買主のそれぞれの視点や要望によっても成約する価格は変動します。
公示は公示。差分=不動産業者の儲けではありません
①~④は公のものですが、通常、不動産を売却する場合の査定では、不動産業界の取引事例(実績)や、物件周辺の事例も加味して算定するのが一般的です。住環境や、物件自体のポテンシャル(人気物件、ビンテージ物件であるとか、管理状態がよいなどの、資産価値といわれる部分)といったものは、不動産のプロ、目利きによって初めて価格に転嫁されるものであり、公示価格と、流通している不動産の実勢価格にだいたいいつも差分が生じるのは、そういった理由からです。
「公示地価や路線価は国が公表している価格だから絶対だ」と考える方はいて、「差分=不動産業者の儲け」という見方をしてしまう、特に高齢者の方には割と多いのですが、不動産業者による査定は、その物件評価の一片の真実であることに違いはありません。
不動産売却の一般的な査定は3パターン
では、⑤実勢価格で動く不動産業界で一般的な物件を売却する場合の査定は、どんな方法で行うのでしょう。方法は、大きく分けて下記の3つがあります。
①原価法
②取引事例比較法
③収益還元法
①は、査定対象の不動産を同じ場所に再建築した場合にかかるコストを割り出し、そこから、最初の建築当時からの経年劣化で下がった価値分を差し引いて、現在の価値を算出するというもの。再建築にかかる金額は「再調達原価」と呼ばれます。
原価法は、要は積算で算出するものなんですね。建物を売却したい場合に用いられ(建物のある土地の場合は計算方法が少し違います)、計算式で表すと、こんな形になります。
積算価格=単価×総面積×残存年数(耐用年数-築年数)÷耐用年数
プロの目によって不動産の価値は変わるもの
ただ、たとえば木造家屋の法定耐用年数は22年ですが、その年月の間、定期的にしっかりメンテナンスして大切に居住してきたような物件は、耐用年数を超えているからといって価値がゼロになるとは実際は考えにくい。築35年の物件でも、築年数以外の部分でむしろ大きな価値を見つけられる場合もあります(ビンテージ物件とは、まさにそういうことです)。その「価値」を見つけるのがプロの目利きの仕事。プロのセンスや感覚、その地域のマーケット状況や、建物の仕様などによって、不動産の価値は変わるものなのです。
②は文字通り、過去の取引事例を参考にして、対象となる不動産の価格を算出する方法です。過去の事例を参考にするため、人気の高い中古マンションや宅地などで使われる場合が多い。③は不動産投資の場面で使われることが多く、不動産の将来的な収益を基に、その価格を算出する方法をいいます。
これだけ査定の方法が様々で、不動産業者も多くの事例を知っているものですから、ある程度、精度の高い査定を出すことは可能です。「まだ売るかどうかわからないけれど…」という前置きがあっても通常は喜んで引き受けてくれるので、気を楽に依頼してみていただきたいと思います。その際は1社だけではなく、比較のために2社くらいに依頼するのがお勧めです。
業者買取価格のメリット、デメリットは理解しましょう
ちなみに、以前相談にいらした方の話ですが、取った査定額が非常に安いことがありました。結果を見せてもらうと「業者買取価格」の設定になっており、気落ちする相談者の方にそれが普通の査定とは違うことを説明した覚えがあります。
業者買取価格は、言うなれば下取り価格のようなもの。確実に買ってもらえ、かつ即金ですが、その分価格は低めです。相談者の方は残債も少なく、売却について一刻を争うような状況ではなかったため、業者買取りではなく、少し時間はかかっても一般ユーザー向けに高く売却したほうがよいのではないかとアドバイスしたところ、実際、査定額よりも数百万円高く一般の方に売却することができました。
業者買取りは内見も一度で済みますし、未公開のまま売却できる、契約不適合責任は免責になる(問題がある物件でも現況のまま買い受けてくれる)などのメリットはありますが、知らないうちに安価に売却してしまうことのないよう、業者買取価格という言葉は覚えておいてください。
査定価格を知りたいけれど、不動産屋に行くのが億劫、周りに店舗がない、誰にも知られたくない、という方には秘密厳守で査定してくれる会社を当NPOでご紹介することも可能ですので、ご相談ください。
また「住宅ローンが払えない」というご相談をはじめ、債務問題、不動産トラブル、投資物件トラブル等でもお困りのことがありましたら、こちらもお気軽にご相談ください。ご相談内容に適したアドバイス、専門家の紹介もすべて無料で行っています。まずは何でも、ご遠慮なくお問い合わせください。
メール、公式LINEでのご相談は24時間受付可能。関東・銀座相談所は、土・日・祝日の無料相談会を行っておりますので、対面や電話でのご相談予約も可能です。
相談所は、関西、中国・四国にもございます。ご相談の場合は各相談室にお問合せください。
【4月の土日祝日無料相談会】
4月27日(日)
10:00~
13:00~
15:00~
17:00~
※面談時のマスク着用は、任意とさせていただきます。
電話、メール、オンライン相談(zoom)もご予約可能です。
【お問合せ・ご予約】
TEL:0120-447-472
お問合せフォーム:
https://www.shiennet.or.jp/database2/contact/